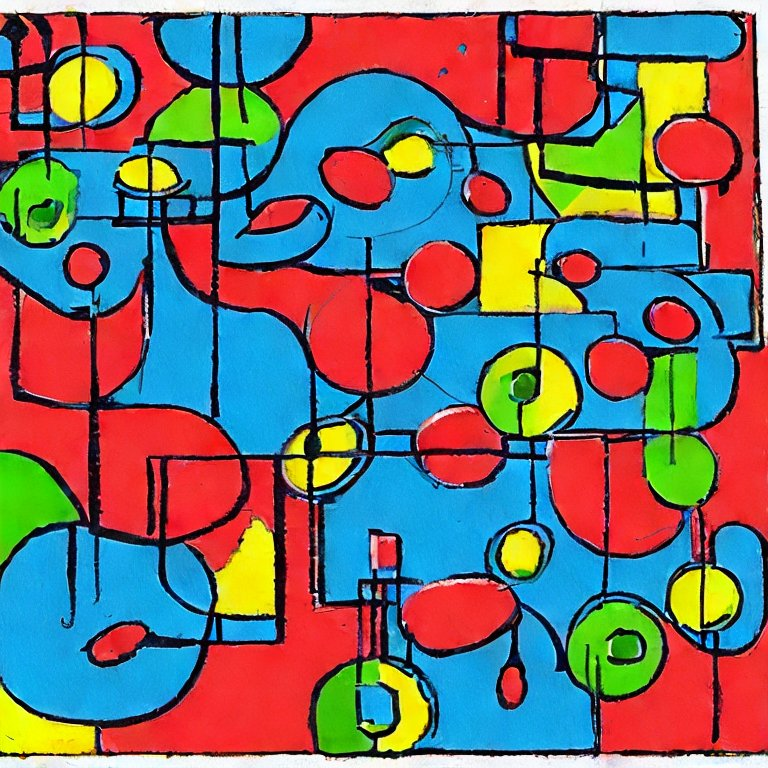
一般に暗号資産は価格変動が激しいため、送金や決済など金融取引にはステーブルコインが用いられる。重要なのは、ステーブルコインは単独では機能せず、他の暗号資産のブロックチェーンネットワークを使って流通する点だ。使用される暗号資産はレイヤー1ブロックチェーンだが、決済コストなどの理由でビットコインは用いられずイーサリアムやトロンが主流だ。暗号資産市場におけるビットコインの取引にも、これらのレイヤー1ブロックチェーン上のステーブルコインが用いられる。
使用したAI:情報収集、Monica Search;文書作成、GPT-4o。
レイヤー1ブロックチェーンを用いたステーブルコインの流通メカニズム
ステーブルコインは、価格の安定性を維持するように設計された暗号資産であり、主に法定通貨にペッグされている。これらはレイヤー1ブロックチェーン上で発行・管理され、スマートコントラクトによって透明性と信頼性が確保されている。
スマートコントラクトは、イーサリアム以降のレイヤー1ブロックチェーンが持つ機能で「ユーザーが一定の行動を取った場合、予め決められた動作を自動的に実行するプログラム」で、いわば契約の自動実行プログラムである。
ステーブルコインには、法定通貨担保型、暗号資産担保型、アルゴリズム型の3種類が存在する。法定通貨担保型は、銀行口座に預けられた法定通貨を担保として発行され、Tether(USDT)やUSD Coin(USDC)が代表例である。暗号資産担保型は、ユーザーが暗号資産をスマートコントラクトにロックし、その価値に応じて発行されるもので、DAIがその一例である。アルゴリズム型は、供給量を動的に調整することで価格を安定させる仕組みを持ち、TerraUSD(UST)が例としてあげられる。
レイヤー1ブロックチェーンは、これらのステーブルコインの発行や取引を支える基盤である。スマートコントラクトを用いて発行や担保管理、供給調整を自動化し、取引は迅速かつ安全に実行される。取引決済の承認システムとしては、PoW(Proof of Work)やPoS(Proof of Stake)、DPoS(Delegated Proof of Stake)がある。PoWはビットコインのように膨大な計算作業を通じて取引を承認する仕組みであり、高いセキュリティを提供する一方でエネルギー消費が多い。一方、PoSはトークン保有量に応じて承認権が与えられ、DPoSは投票によって選ばれた代表者が承認を行う仕組みである。これらの方式は、ステーブルコインの安全で効率的な流通を支えることができる。
レイヤー1ブロックチェーンは、ステーブルコインの決済基盤としての役割を果たし、将来的には(暗号)資産としての価値よりインターネットのインフラストラクチャとして進化する可能性が高い。ネイティブトークンは、ガス料金(決済コスト)やネットワークのセキュリティ維持、ガバナンスのためのトークンとしての役割がより強くなるだろう。この辺の事情については、以前に「デジタル社会における暗号資産の価値 - 精密医療電脳書」で述べた。
ステーブルコインが利用しているレイヤー1ブロックチェーン
主なレイヤー1ブロックチェーン
ステーブルコインは、複数のレイヤー1ブロックチェーン上で発行・流通している。特に利用が多いのは以下のチェーンである。いずれも承認システムはPoS/DPoSであり、高コストのビットコインを含むPoWのブロックチェーンはほとんど用いられない。
イーサリアム(Ethereum)
ステーブルコインの流通において、依然として重要な存在である。特にDeFi(分散型金融)分野において広く使用されている。
トロン(Tron)
ステーブルコイントランザクションが最も多く行われているチェーンであり、特にUSDT(テザー)の利用が顕著である。
バイナンススマートチェーン(BNB Chain/BSC)
取引コストの低さから人気があり、トロンやイーサリアムに次ぐ規模の利用がある。
ソラナ(Solana)、アバランチ(Avalanche)、ポリゴン(Polygon)
これらのチェーンは全体のシェアとしては比較的小さいが、特定の用途や分野で注目されている。
各レイヤー1ブロックチェーンの使用比率
ブロックチェーン分析企業Chainalysisの2024年レポートによると、ステーブルコインの取引は以下のようなブロックチェーン上で行われている。技術的には
トロン(Tron):約50%
トロンは、ステーブルコイン取引の約半数を占めており、特にUSDTが多く利用されている。
イーサリアム(Ethereum):約30%
イーサリアムは、DeFiやNFTエコシステムでの利用が多く、引き続き大規模な流通を維持している。
バイナンススマートチェーン(BSC):約10%
手数料の低さが特徴であり、取引量はトロンやイーサリアムに次ぐ規模である。
その他(ソラナ、アバランチ、ポリゴンなど):約10%
全体のシェアは比較的小さいが、特定のユースケースで利用されている。
これらの比率は、USDTやUSDCなど主要ステーブルコインのオンチェーン流通量やトランザクションベースで算出されている。
ステーブルコインとレイヤー1ブロックチェーンの関係
ステーブルコインの使用目的やネットワーク手数料、スピードなどによって利用されるレイヤー1ブロックチェーンが選ばれる傾向がある。例えば、トロンは高速かつ低コストなトランザクションを実現しており、取引所間の裁定取引やクロスチェーン送金で多用されている。一方、イーサリアムはそのエコシステムの広がりから、DeFiやNFTの分野での利用が多い。
参考文献
CoinDesk Japan:2024年ブロックチェーン活用事例──5分野から見える実用化
ステーブルコインのご紹介 | Global X Japan