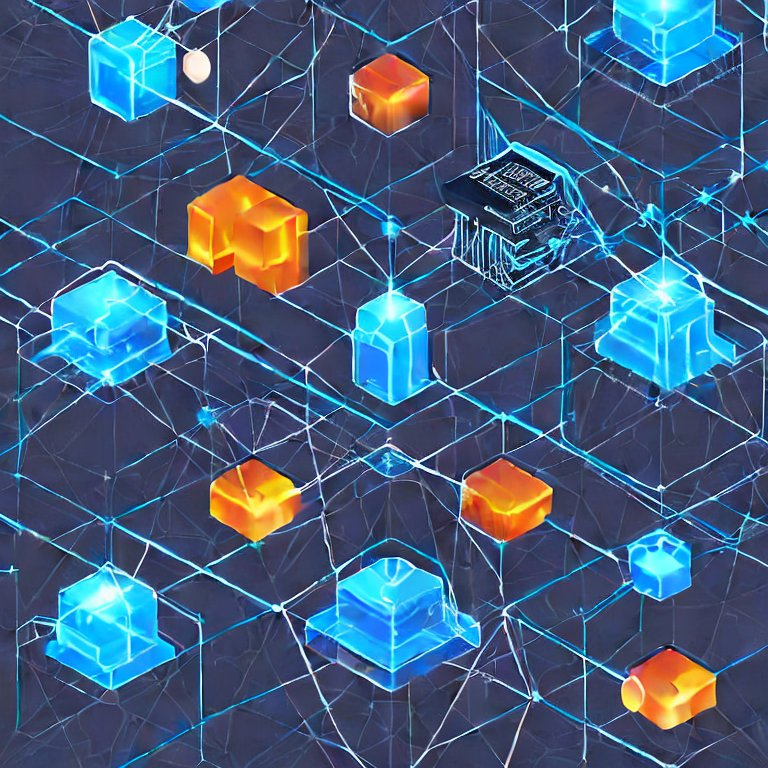
暗号資産(仮想通貨)は現在の金融システムを根底から変革する技術革新だが、その手始めとしてステーブルコインに関する法整備が始まった。米国では「米国ステーブルコインの国家的イノベーションの指導と確立法案」(GENIUS法案)が3月13日に可決さされた(米上院委員会、ステーブルコイン法案を可決)。日本でも法改正が進んでいる(金融庁、暗号資産・ステーブルコイン規制改正法案を国会提出──「仲介業」など新設へ)。
ステーブルコイン(Stablecoins)とは、その価格が法定通貨、または市場で取引されるコモディティ(貴金属や工業用金属等の商品)などと連動(ペッグ)するよう設計されている暗号資産である。流通にはイーサリアムやトロンなどのレイヤー1暗号資産ネットワークを使うので、技術的にはこれらのブロックチェーン技術に依存することになる。トランプ政権は中央銀行デジタル通貨 (Central Bank Degital Currency) を金融を監視するものとして否定し、ステーブルコインを促進する政策をとっているが、次の論考では現在既にデジタル通貨の監視体制は進行していて、ステーブルコインはその監視体制を強化するものだ、としている。
brownstone.org
米ドルはすでにCBDCとして機能しているのか
著者のAaron Dayによると、92%以上が連邦準備制度理事会および商業銀行のデータベースにデジタルエントリとしてのみ存在しているため、米ドルはすでに中央銀行デジタル通貨(CBDC)として機能している。このデジタルドルシステムは、HSAやEBTカードなどのメカニズムを通じてすでにAIに追跡されており、カナダのトラック運転手の抗議行動のようなイベントに見られるように、監視と検閲を可能にしている。STABLE法のようなステーブルコイン法案は、この監視の枠組みをさらに強固なものにし、すべての取引に厳格なKYC(know your customer:使用者の同定)追跡を義務付けることになる。
CBDCとステーブルコインの根本的な違い
直接通貨を管理する中央銀行デジタル通貨(CBDC)と、米国のステーブルコインを間接的に管理する方法には、いくつかの違いが存在する可能性がある。まず、発行主体と信用構造の根本的な違いが挙げられる。CBDCは中央銀行が直接発行する「国家デジタル債務証明書」であり、国家信用が直接裏付けられている。一方、ステーブルコインは民間企業がドル預金や国債で裏付けており、発行企業の健全性と資産保管機関の信頼性という二重の信用リスクを抱えている。
監視強度の技術的限界
次に、監視強度の技術的限界が挙げられる。CBDCは完全な追跡可能性を持ち、取引履歴の遡及的監査が可能な「制御可能な匿名性」を採用している。一方、ステーブルコインは不完全な監視であり、取引所を経由しないP2P送金は追跡困難である。
国際競争力学の相違
国際競争力学の相違も見られる。CBDCは、中国やEUが主導する「デジタル通貨ブロック形成」のツールとして機能しており、BRICS加盟国間の相互決済に利用されている。一方、米国ステーブルコイン戦略は、ドル覇権のデジタル延命策として位置づけられている。
金融政策への影響度の違い
金融政策への影響度も異なる。CBDCは直接的に操作可能であり、理論上はマイナス金利を直接適用することができる。一方、ステーブルコインは間接的な影響しか及ぼさず、金融政策への影響は限定的である。
法執行の実効性ギャップ
法執行の実効性ギャップも存在する。CBDCは即時凍結機能を持っており、短時間で資金を無効化することが可能である。一方、ステーブルコイン規制には抜け穴があり、非保管型ウォレットでの資産保持は実質的に規制できない。
結論:現実的課題と今後の展望
結論として、Aaron Dayの論考には限界と現実的課題がある。技術的にステーブルコインにはCDBCの持つ完全な追跡可能性や即時凍結機能はない。またステーブルコインが米国のドル延命策の一貫である、という視点がかけている。たぶん問題の核心は「監視vs自由」の二項対立ではなく、国際競争下での規制バランスである。すなわち米国はドル維持のためステーブルコインを推進するが、EUや中国はユーロ、人民元の推進のためCDBCを推進する、という解釈が妥当である。
注:この論説はAaron Dayの論考をDeepSeekに批判的論考をさせた結果(箇条書き)をApple Inteligenceで文書化、さらにchatGPTで平易にしたものである。Apple Inteligenceの出力を下記に掲載しておく。LLMはChatGPT登場時ちょっと使ったが、プログラミングには使えるが、文章作成ツールとしては、あまりメリットがない、という印象だった。今回使ってみると、かなり様相が異なった:論理的に思考が可能で入力を調整することにより、自分の欲しい情報が引き出せるようになっている。工夫は必要だが、地球上の情報空間全体から効率よく情報収集できるだろう。
著者のAaron Dayによると、92%以上が連邦準備制度理事会および商業銀行のデータベースにデジタルエントリとしてのみ存在しているため、米ドルはすでに中央銀行デジタル通貨(CBDC)として機能している。このデジタルドルシステムは、HSAやEBTカードなどのメカニズムを通じてすでにAIに追跡されており、カナダのトラック運転手の抗議行動のようなイベントに見られるように、監視と検閲を可能にしています。STABLE法のようなステーブルコイン法案は、この監視の枠組みをさらに強固なものにし、すべての取引に厳格なKYC(know your customer:使用者の同定)追跡を義務付けることになる。
直接通貨を管理する中央銀行デジタル通貨(CBDC)と、米国のステーブルコインを間接的に管理する方法には、いくつかの違いが存在する可能性がある。この著者の意見が必ずしも正しくないと仮定すると、まず、発行主体と信用構造の根本的な違いが挙げられる。CBDCは中央銀行が直接発行する「国家デジタル債務証明書」であり、国家信用が直接裏付けられている。例えば、中国人民銀行のデジタル人民元が挙げられる。一方、ステーブルコインは民間企業がドル預金や国債で裏付けており、発行企業の健全性と資産保管機関の信頼性という二重の信用リスクを抱えている。例えば、USDCが挙げられる。著者の盲点として、連邦準備制度のデータベース支配説は、商業銀行の信用創造メカニズムを過小評価している。実際には、米ドル流通量の60%が民間銀行預金で創造されている(FRB St. Louis調べ)。
次に、監視強度の技術的限界が挙げられる。CBDCは完全な追跡可能性を持ち、中国人民銀行の例では、取引履歴の遡及的監査が可能な「制御可能な匿名性」を採用している。一方、ステーブルコインは不完全な監視であり、例えばUSDCのブロックチェーン分析では、取引所を経由しないP2P送金は追跡困難である。2024年のChainalysis報告書によると、主要ステーブルコイン取引の23%が非KYCウォレットを経由している。
国際競争力学の相違も見られる。CBDCは、中国やEUが主導する「デジタル通貨ブロック形成」のツールとして機能しており、例えばBRICS加盟国間の相互決済に利用されている。一方、米国ステーブルコイン戦略は、ドル覇権のデジタル延命策として位置づけられており、Circle社の2025年Q1決算では、USDCの国際送金の47%が新興国向けである。著者への反論材料として、国際決済銀行(BIS)の2024年調査では、ステーブルコインが途上国の送金コストを62%削減した(フィリピン事例)。
金融政策への影響度も異なる。CBDCは直接的に操作可能であり、理論上はマイナス金利を直接適用することができる(スウェーデンRiksbank検証実験)。一方、ステーブルコインは間接的な影響しか及ぼさず、2025年3月現在、USDCの流通量($250億)は米マネーストック(M2)の0.15%に過ぎず、金融政策への影響は限定的である。連邦準備制度のWaller理事は2025年2月に、「ステーブルコインは現行銀行システムの補完物に過ぎない」と述べている。
法執行の実効性ギャップも存在する。CBDCは即時凍結機能を持っており、ナイジェリアeNairaでは2023年の反政府デモ参加者の資金を90分で無効化した。一方、ステーブルコイン規制には抜け穴があり、非保管型ウォレット(例:Ledgerデバイス)での資産保持は実質的に規制できない。2024年のTether社の法務対応では、米司法省要請への平均対応時間が17営業日であり、現金没収の即時性と比較して非効率である。
結論として、著者の論には限界と現実的課題がある。技術決定論的バイアスとして、ブロックチェーンのイノベーション速度を過小評価している。例えば、Zk-SNARKsによるプライバシー強化が挙げられる。地政学的視野の欠如として、米国がステーブルコイン規制を緩和すれば、シンガポールやスイスが代替ハブ化する現実的リスクがある。経済インセンティブの無視として、監視強化より「ドルデジタル覇権維持」が政策優先事項であるFRB内部文書の分析不足がある。歴史的類推の誤謬として、1933年の金没収令との比較は、デジタル資産のグローバル流通性を考慮していない。真の課題は「監視vs自由」の二項対立ではなく、国際競争下での規制バランスを模索することである。国際通貨基金(IMF)の2025年4月報告書は、ステーブルコインを「途上国の金融包摂ツール」と位置づけており、著者の悲観論とは異なる現実が進行中である